種村季弘による「『にせあぽりや・触手』論」 [小田仁二郎]
27日のこと、「小田仁二郎と宮内」の資料を私設宮内郷土資料館「時代(とき)のわすれもの」の鈴木孝一さんに持って行って、貴重な仁二郎関連資料をお借りしてきました。『器怪の祝祭日―種村季弘文藝評論集』(沖積舎 昭59)と『時間と空間』という上田周二主宰の同人誌第16号(昭60)です。前者は立派な装丁の箱入り本。「ある老胎児の回想」として『触手』の内容に深く立ち入っての7ページにわたる評論。福田恆存による巻末解説は別として、『触手』の紹介としては私がこれまで知った中で群を抜いてダントツです。初出は「週刊読書人」昭和55年1月21日号。
まとめの部分を写させていただきます。
《主題からいえば酸鼻をきわめる血の頽廃を書いた自然主義小説にそっくりでありながら、現実に見合う力のない未生児の追憶として書かれているので、すべてがもはやない世界として現前しており、あるいはこの未生児は死産児として流されることになるのだから、これから先もあり得ない世界として現前している。書かれた内容を裏切って、作品の読後感が一種あえかな王朝風のみやびを喚起するのはそのためだ。あえていうなら『桜の園』の透明な終末感、いや、見渡せば花も紅葉もない藤原定家の匂いたつ虚無の香りが、血と精液にまみれたむごたらしい宴のあとに立ちこめる。死母の巨大な汚洞は、それが生み出した無惨な人間と現実を呑み込み破壊しはするが、同時に言語として虹のような七彩の夢を吐き紡ぎ出すのである。それかあらぬか「触手」の文体は、どこか一切が終った後にはじまる新古今調の有心体の今日的な立ち帰りを思わせないでもない。生(なま)の官能をことごとく鏖殺(おうさつ―皆殺し)しおえた後に来る言語の官能の響きである。しばしば誤解されてきたように、小田仁二郎は肉体派文学の旗手ではなかった。》(64p)
この文の後に「にせあぽりあ」の「にせ」の解明の文章がつづくのだが、そもそもこの評論の書き出しが《アポリアといえば行手に通うべき道なきこと、すなわち八方塞がりであり、転じて難問の意である。》(59p)で始まり、さらに中で《難解なのは・・・出口という出口をしらみつぶしに塞いでは自ら作り上げた八方塞りを手探りにひとつひとつ確かめている、不可解な作業だったのだろう。どこにも抜け道のない、すなわちアポリアと化した言語空間。》(60p)《連用止めの不安なたゆたいはもはや日常と見紛うまでに安定している。この文体に閉ざされた世界は、したがってどこまでも遅延された八方塞り、出口なしなのである。》(63p)とある。
先の文(64p)にはこうつづく。
《すでにして母胎は生み出すべき何物も孕むことのない空の器である。昭和初年代文学の帰結として、小田仁二郎は、このもはや何もない、何ひとつ起り得ない場所に逢着した。そこから先には何もないどん詰り、袋小路である。それはしかし生(なま)のものの生成に関する限りであって、言語の生成についてはその限りではない。かえってすべてのものが死に絶えたからこそ何かを言う、というのが悲歌の、鎮魂歌のあり方である。だからこそアポリアではなくて「にせあぽりあ」であった。》(64p)
昭和23年の初出では「にせあぽりや」だったのに、私の中でもそうだったが、ここでも「にせあぽりあ」になっていることはともかく、種村氏が言うのは、仁二郎は「袋小路」の先に文学の未来を賭けたということだろうか。『にせあぽりや』に描かれた宮内の記憶は仁二郎にとってまさに「生のもの」であり、そこをとことん解体したあとに構築されたのが『触手』の世界だった。そう考えると『にせあぽりや』の終章、《町は廃墟となり銀杏の大樹に変じた。私の町は一樹の銀杏と化したのである。猛然と竜巻が砂塵をまきおこし、銀杏も廃墟も一瞬にしてその底に壊滅した。》(『にせあぽりや』109p)も得心がゆく。なるほど、そのあとこう締めくくられて「触手」に入ることになる。
《それから私は、北むきの暗いまどの部屋にたちもどり、闇のなかに坐りつづけた。・・・その夜ふけ、私は北むきの部屋を闇にのこし、網の目のように都会にはりめぐらされる線路のうえに、自分の胸をおいた。重さもなく、軽さもない巨大な機関車が、私の胸のうえをよぎったせつな、鮮やかな紅の血潮がほとばしり、その血は、暗黒のなかにひかりかがやくばかり、そこに、私の姿をえがきだした。私の血潮でえがかれた私が、指のさきから、きらめく血をしたたらせながら、私の屍には一瞥もくれず、茫々たる闇のなかに、すたすた歩みさるのである。屍は水となって線路のうえに溶けた。
にせあぽりや――。》(111p)
機関車に轢き殺させた自分の身体からほとばしる血潮は、「暗黒のなかにひかりかがや」いて新たな「私の姿」を現出させる。「きらめく血」によって描き出される「ほんとうの私」からみれば、「生の私」がいかに難問(アポリア)に見えようとも偽物に過ぎない。ほんとうの難問はこれから始まる。指の先からしたたる「きらめく血」をしたたらせつつ歩みとなるはずである。かくして第二段「触手」へとつながってゆく。したがって「触手」は、その指の先の描写から始まらなければならなかった。こうして全体の大きな構図が見えてきた。『触手』全体の解読の手がかりを得たと感じた。あらためて《わからないとは何であるか。わかろうとしないことである。精神の怠惰にすぎないのではないか。》(小田仁二郎『文壇第二軍』)の言葉の意味するところの重さに思い到る。真善社版『触手』は「にせあぽりあ」と「触手」が一体となって読み解かれることを待望している。種村氏の文章が昭和55(1980)年、『触手』が世に出てすでに30年が経っていた。さらにそれから35年のいま、時代はようやく小田仁二郎に追いつきつつあるのかもしれない。
種村氏の文章を最後までつづけます。
《この空の器からはあらゆるものが言語として取り出せる。そして太宰治ほど終末の意識をナルしスティックな自家消費に使い尽したのではない小田仁二郎の場合には、空にするまでが自分の作業であっても、空の器から言葉を取り出すのがかならずしも自分でなくてもよかった。自分であってもよかったが、戦後の作家は職業作家として空から花を咲かせることにそれほど躍起ではなかったようだ。その代りに同人雑誌の教育家として他人に花の栽培を譲ろうとしたのかもしれないが、そこから巣立った某女流の仕事に通じていない私には、これを何とも言うことができない。
ただ、ある双生児的な並行現象がかなりかけ離れていると見えるところで起った。『触手』の後四半世紀を経て書かれた三島由紀夫の『天人五衰』である。この作品にも三保の死んだ暗い海の寄せ返す終末意識のうねりがくり返し起伏しながら、結末において記憶も何もない小さな庭に一切が収斂して行く。この何もない庭もまた、奇術師の空っぽのシルクハットのように、そこから何でも取り出すことのできる空の器である。あるいはそのはずである。》(65p)
高橋和己は『触手』と埴谷雄高の『死霊』とを両極に並べたが、種村氏は『触手』と三島由紀夫の『天人五衰』の出現を「双生児的な平行現象」とみた。いま、「種村季弘 三島由紀夫」で検索して、私と同世代の池田香代子さんの種村さんへの弔辞を読んだ。思わず涙が出そうになる弔辞だった。すごい人だったようです。「種村季弘 小田仁二郎」で検索したら《岩橋邦枝の旦那が、種村季弘の飲み友達で、結婚式に出席したら、媒酌人が瀬戸内と小田仁二郎で、種村さんは「触手」の作者を尊敬してゐたので、式の間ずつと小田を観察してたといふ話。》というのがあった。その種村氏をして並々ならぬ関心を抱かせしめた小田仁二郎という存在であったわけです。
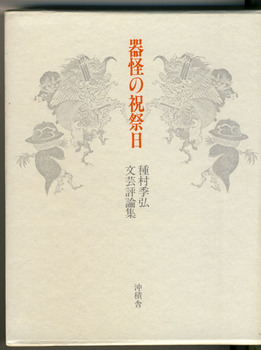




コメント 0